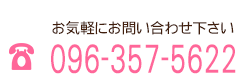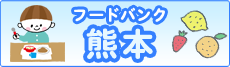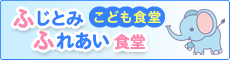- トップ
- 園での生活
施設ギャラリー
保育園の一日
※クラス・季節・行事等により、時間・内容が変動します。
※開園~8:30と4:30~閉園の間は合同保育です。
※保育標準時間認定の方も保育短時間認定の方も、基本の流れは変わりません。

給食風景

子どもの元気の源は食事から
何よりも食は健康の基礎となりますので食材も畑で採れた食物を使用し調理しています。
離乳食を終えた子どもは毎日バランスの取れた約8品のメニューをバイキング形式で出しています。
給食

・「楽しく食べる」を目標に、毎日の食事や様々な行事、菜園活動やクッキング活動などを通して食育に取り組んでいます。
・季節の食材・地産地消を心がけ、栄養士による栄養管理のもと、月曜から土曜まで保育園で調理したバランスの良い食事を温かい状態で提供しています。
・様々な食品を少しずつでも食べることができるように、調理の工夫やメニューの品数を多くしています。
・できる限りご家庭と同じ雰囲気で食事をするために、食器・食具類は年齢に合わせて、陶器やガラス・木などの天然素材の物を主に使っています。
・お子様の誕生会では、保護者の方にも保育園の給食を食べていただく機会を作っています。(給食費300円が必要です)
- アレルギー対応
- アレルギー体質のお子様には特定の食品を取り除く「除去食」を提供しています。
- 「除去食」希望の方は医療機関で「保育園生活管理指導票」を発行してもらい、保育園に提出してください。
年度途中に食物アレルギー症状を発症した場合でも同様です。
「保育園生活管理指導票」の提出が無いお子様の給食に関しては、対応できないこともあります。
- 衛生管理
- 調理担当者は毎日の衛生管理を行っています。調理前に厨房の衛生確認・担当者の衛生確認を行います。食品の搬入時は、必ず検品を行い鮮度や産地や異物の混入がないかを確認しています。食器や調理器具は熱や紫外線による殺菌処理をし、厨房は毎週2回の害虫駆除をしています。
- 調理中は厨房や食材の温度を確認し、提供する30分前には検食をしています。
- 調理担当者は毎日の健康チェックと毎月の検便を実施しています。
- 0・1・2歳児
- 乳児の粉ミルクは保育園で用意します。
特殊な銘柄の場合はご相談ください。 - 離乳食は家庭と連携しながら進み具合を確認し、お子様の育ちに合わせて調理した中期食・後期食・完了食を提供しています。
- 午前と午後におやつがあります。
- 3・4・5歳児
- 平日はバイキング形式で食事をしています。自分で「食べきれる量」が分かってきます。苦手な食品でもチャレンジしやすいように工夫しています。
- 完全給食の提供ができます。保護者のご希望があれば主食(ご飯類)の提供や食器・食具の準備をしています。(希望者のみ対応・別途料金がかかります)
- 毎日の食事の準備(米とぎ・テーブルセッティング)や畑で野菜の栽培活動、クッキングを通して「食育」に取り組んでいます。
- 午後におやつがあります。
保育園の運営費には3歳児からの主食費が含まれていません。ご家庭からご飯を持参するというのが普通ですが、当園は食育を大切にしており、温かいご飯を提供することで、メニューが広がり、豊かな食事の提供ができるようになります。朝からご飯を炊かないご家庭への負担軽減やご飯忘れのお子様の精神面にも配慮したサービスです。この費用には材料代・光熱水費・人件費・食器や食具代が含まれます。
安全管理
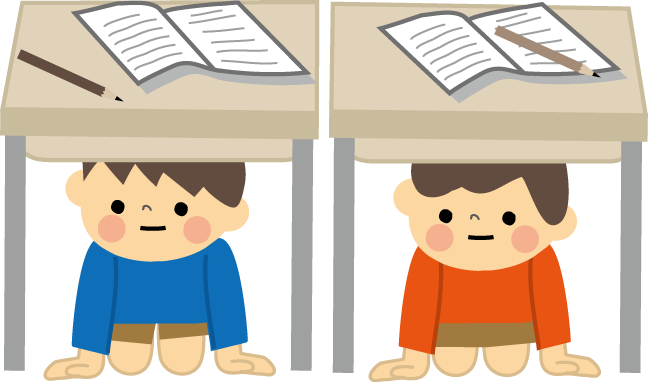
お子様を災害から守るために年間計画に基づいて毎月の訓練を実施しています。 「安全管理委員会」を組織しており、安全を確保する ための体制作りに努めています。
避難訓練(毎月1回以上)
火災や地震などを想定し、「大切な命」を守るために何をしたらよいか、臨機応変に対応できるよう毎月の訓練で避難方法を学びます。また、不審者が侵入した場合を想定した対応についても訓練を行っています。 年1回は消防署立会いの防災訓練を行い、指導を受けています。
交通・安全指導(毎月1回)
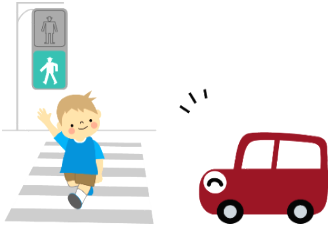
日頃の保育の中で道路の安全な歩き方や横断の仕方を分かりやすく指導しています。また、日常の生活の中で安全な過ごしかた を学びます。 年1回は市の交通安全教室を受けています。
事故防止
毎月の安全点検(園舎・園庭・遊具・備品など)を行っています。
保育中は事故の無いように気を付けていますが、万が一の事態に備えて園児の保険に加入しています。
誤飲防止のため、教材等の整頓・管理をしています。
SIDS(乳幼児突然死症候群)対策として、乳児には無呼吸センサーを義務付ており、全園児の睡眠時には呼吸の確認と記録を行っています。
健康管理
元気で楽しい生活が送れるよう、年間計画に基づいて健康管理や保健的な環境づくりを行っています。「保健衛生委員会」を組織しており、保健的で健康に過ごせるための体制作りに努めています。
健康観察と保健衛生
毎朝の健康観察では、お子様が保育園で元気に活動できるかどうかを観察し、 保護者の方に検温して頂きながらお子様の様子を聞き取ります。
保育中に熱(平熱より1度以上の上昇)が出たり、体調がすぐれない場合はご家族に連絡をし、今後の対応を相談します。
感染症が疑われるときは、医師の診察をお願いすることがあります。
健康な体のために、年間を通して外気温と室内温度の差が+-5℃以内になるよう調節しています。
(室温の目安:夏期→27~28℃ 冬期→20℃)
早寝・早起きを心がけ、朝食は必ず食べてから登園させましょう。
清潔の習慣を身につけましょう(歯磨き・顔洗い・爪切り・入浴・着替え等)
定期検診や予防接種は必ず受け、保育園にも結果の報告をお願いします。
健康診断
内科検診→年2回(4月、10月)実施
栄養状況・脊柱・心臓疾患及び異常・皮膚疾患・その他の疾病及び異常について診断を受けます。
嘱託医:池沢小児科医院 池澤 誠氏
歯科検診→年2回(5月、11月)実施
歯数・その他の歯疾・口腔の疾病及び異常について診断を受けます。
嘱託医:赤城歯科医院 赤城 公徳氏
健康診断は在籍の全園児が受けなくてはいけません。結果の記録・保管をし、 受診後は文書での伝達とお子様の出席ブック記入欄に転記してお知らせします。
衛生管理
毎朝、担当者による施設内の衛生確認をしてから始業します。
手洗い後はペーパータオルを使用しています。食事の際は一人ひとりにお手拭きを準備し、保育園で洗濯・乾燥させています。
歯ブラシは使用後に洗浄し、歯ブラシ専用の殺菌保管庫にて管理しています。
感染症などの拡大を防ぐために、次亜水にて室内の衛生環境を整えています。
(当園で使用している次亜水(弱酸性次亜塩酸酸水)は、人にやさしく菌に強い水です。用途に合わせて希釈して使用します。噴霧器は各部屋に設置し、超音波で室内に噴霧することで、空間殺菌と加湿効果があります)
感染症について
感染症が疑われる場合は早めに医師の診察を受けてください。医師の指示に従い、ご家庭で安静にして回復を待ちましょう。
流行している感染症に関する情報や園内での感染を確認したら、園内の掲示板にて発生状況と病気情報を掲示し、迅速にお知らせします。
以下の感染症に罹ったらお子様の安静と園内感染防止のため、登園できません。
- 第1種学校伝染病
- 第2種学校伝染病
- ・インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- ・風疹・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・新型コロナウイルス感染症
- 第3種学校伝染病
感染症の症状が和らぎ、集団生活に支障のない状態に回復したら、医師から登園の可否を判断して頂き「意見書」を書いてもらい、保育園に提出し、登園が可能となります。(「意見書」は感染症に罹った場合、次の登園の際に必要な書類です。 用紙は入園後に配布しますので、ご家庭で保管・コピーし、病院受診の際は持参して医師に記入をしてもらってください。)
薬について
保育園は「健康なお子様をお預かりする施設」です。原則として保育園での与薬はできないことになっています。しかし、どうしても必要な場合は薬を処方した医師から「与薬指示書」を書いていただき、保護者は「与薬願い」に記入・捺印し、保育園に提出してください。
お薬は1回分のみお預かりします。袋には必ず園児名を記入し、職員に手渡しされたお薬のみ保管し、保護者に代わって与薬をいたします。
いかなる場合であっても座薬はお預かりできません。
ご相談窓口
保育園での保育は、お子様を中心にご家族と保育園が良好な協力関係を築き、より良い環境をつくりだす努力の中に成り立つものと考えます。このため、当園は保護者のご意見やご要望、苦情や不満などをしっかりと聴き、子育てのご相談などにも対応出来るよう努めます。ご遠慮なさらずに園長・主任保育士はじめ、相談しやすい職員にお声かけください。
苦情解決の仕組みについて(目的)

- 意見・要望・苦情等への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足度を高める
- 早急に苦情等への対策を講じ、利用者個人の権利を擁護し、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。
- 納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努める。
解決のための園内体制について
当園は園長をその責任者とし、主任保育士(髙濵)を受付担当者としています。
第三者委員について
保育園に直接言いにくいことや何度言っても解決しないようなことを解決するため、次の2名の方に第三者委員を依頼しました。苦情等の解決に対し社会性や客観性を確保し、利用者の立場に配慮した支援をしてくださいます。
- 第三者委員
- 川口 延子 かわしりこども園 園長
- 佐藤 智子 御船町 民生委員